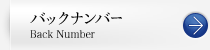OBT 人財マガジン

2012.10.24 : VOL150 UPDATED
-

人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)モノやサービスが溢れ、経済が成熟化した今、顧客と強い絆を結ぶ鍵は何か。今回はその手がかりを求めて、前リッツ・カールトン日本支社長の高野登さんにお話をうかがいました。リッツ・カールトンはホスピタリティを中心とした理念を掲げ、独自のブランドを築き上げたことで知られるホテルです。顧客の心に徹底して寄り添うその企業姿勢には、あらゆる業界に通じる貴重なヒントが潜んでいます。現在は、人とホスピタリティ研究所所長としてホスピタリティに基づく生き方を提唱する高野さんに、これからの時代に求められる人と組織のあり方について語っていただきました。(聞き手:OBT協会代表 及川 昭)
-
[及川昭の視点]

長い間、いろいろな企業で組織変革や競争優位作りなどにかかわっていて思うことがある。例えば、競争優位=差別化だとすると、どんなに頑張っても昨今は機能面だけで違いを出すというのは極めて難しくなってきている。 そうすると結局行きつくところは、サービス業はもとより、製造業、流通業、或いは医師や弁護士といったある種の専門性を持っている人達でも「ホスピタリティ」的なものが、その優位性や差別化という意味でも重要な能力となってくる。
高野登氏が、「ホスピタリティとは、OSである」と仰っているとはとても納得感がある。聞き手:OBT協会 及川 昭
企業の持続的な競争力強化に向けて、「人財の革新」と「組織変革」をサポート。現場の社員や次期幹部に対して、自社の現実の課題を題材に議論をコーディネートし、具体的な解決策を導き出すというプロセス(On the Business Training)を展開している。 -
NOBORU TAKANO

1953年生まれ。プリンス・ホテルスクール(現日本ホテルスクール)卒業後、渡米。NYプラザホテル、LAボナベンチャー、SFフェアモントホテルなどの名門ホテルでマネジメントを経験し、1990年にザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わる。1994年にリッツ・カールトン日本支社長に就任。1997年にザ・リッツ・カールトン大阪、2007年にザ・リッツ・カールトン東京の開業をサポート。2009年に退社し、長野市長選に出馬するも651票差で惜敗。同年、人とホスピタリティ研究所を設立し、日本各地で人財、組織、地域づくりのサポートを行っている。『リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間』(かんき出版)など著書多数。2012年8月に『リッツ・カールトンと日本人の流儀』(ポプラ社)を上梓。
-
ホスピタリティは「資質」ではなく、訓練で強化できる「能力」
────私は仕事柄、毎日多くのビジネスマンにお会いしますが、ホスピタリティがある人とまったくない人と、人は2つに分かれるように思います。何が違うかといえば、他人といい関係を築ける能力や、他人の幸せに喜びを感じる能力、相手の状況に身を置いて考えられる能力といったものが前提にないとダメなのではないかという気がしておりましてね。これは履歴書には特技として表現出来ない能力ですが、大変な能力だと思うんです。こうした能力は学習して身につくものなのかどうか、高野さんはどうお考えになりますか。
身につくと思いますね。例えば、私が生まれ育った長野の田舎では、年寄りの知恵が次の世代をつくるという、日常の中でのトレーニングがありました。田植えや稲刈りは村の人が総出でやるのですが、それぞれお互いの田んぼを見ているんですね。「あいつのところがそろそろ稲刈りだ」となると、誰彼ともなくその日を空ける。同じように、自分のところの稲刈りが近づけば、自然とみんなが集まってきてくれる。こうしたことが当たり前に行われて、子どもたちはそれを見ながら育っていく。これが心のトレーニングになるのです。
また昔は、ガキ大将がいましたよね。学校帰りにみんなで道草をくったり、いたずらしたり。お腹が減っているから、キュウリ畑に入っていったりするわけです。そのときにガキ大将が、「大きいのを取れ」と言うんです。育ちすぎて商品にならないものをちゃんと知っていて、ちょうどいい大きさのものは絶対に取らせない。農家の人もそれがわかっているから、あまり怒らないんです。
これも、ホスピタリティに則っていますよね。こうした感性は、性格や性質だと捉えられがちですが、僕は鍛えることができる能力だと考えています。昔は遊びにもこうしたルールがあって、子どもたちは鍛えられながら大きくなっていきました。こういう社会が健全なんですよ。
────以前、養老孟司さんのお話を聞いたときに、この手の能力を「私は教養だと思う」と言っておられました。こうした感性が備わっている人が、教養ある人なのだと。いい表現だと、とても印象に残っています。
僕の中の教養の定義は、「大人の感性」です。ですから、子どもに教養を「強要」してもダメなんです(笑)。子どもの段階は「教育」です。とにかく教えて育てるしかない。その教えが積み重なって成熟した大人を育て、成熟した社会をつくるというのが本来ではないかと思いますが、今は大人が少なすぎますね。
────さきほど言われたような地域社会も失われつつあります。人と触れ合わないまま大人になった人の感性を、企業が採用後に育てることはできるでしょうか。
不可能ではないと思います。身体の筋肉は、高齢でも訓練すれば強化できることが証明されていますよね。同じように、心も鍛えてこなかっただけのことですから、きちんとトレーニングをすれば育ちます。ただ、その方法は難しいですね。途中で心が折れてしまうこともありますから、かなりしっかりとしたトレーニングが必要です。
その仕組みをつくったのが、リッツ・カールトンなのです。52週間、つまり1年間にわたって行う「ラインナップ(朝礼)」がそれで、毎日15分から20分間行う朝礼でクレドカードから一つのテーマを取り上げ、それに対する考えを自分の言葉で発表させるのです。人と触れ合わないことで一番衰えるのは、人のことを考える筋肉です。それを鍛えるには、人のことを考えさせる仕組みが必要だということです。
土台を築く過程では「力技」も必要
────ザ・リッツ・カールトン大阪を開業されたときには、新規に採用された方のうちホテル経験者は何割くらいおられたのですか。
未経験者は全体の数%いたかどうか、ほとんどがホテル経験者でしたね。
────他のホテルの経験がある方にクレドを浸透させるのは、簡単なことではなかったと思います。具体的には、どのようにして伝えていかれたのでしょうか。

それには「力技」が必要です。先ほどお話したラインナップもそうですが、毎日、強制的に話をさせるわけです。スタッフが自主的に発表していると思われているようですが、それは開業から何年か経ったときの話であってね。始めから思いを持っている人ばかりではありませんから、まずはこちらが思いを語り、その思いをまだ自分のものにできていない人にも、とにかく自分の言葉で発表してもらう。最初はそういったプロセスが必要なんです。
また、ザ・リッツ・カールトン大阪では、休憩時にペットボトル飲料を飲むときには、ボトルに直接口をつけてはいけないといったルールも設けました。グラスに注いで飲むのが、日本人本来の美しい所作です。日頃のそうしたことから徹底しないと、お客さまの前できちんとした立ち居振る舞いはできません。
当時、リッツ・カールトンは日本ではまだ知名度が低く、「外資系のホテル」といった印象でしたので、我々は日本人以上に日本人らしくあろうと。教養や所作、しつらえや装いといったことを意識して、徹底して身につけていきました。
────変化はどれくらいで現れるものですか。
2年近くはかかりますね。ただ、人によって差があり、経験が少ない人の方がやはり早く吸収します。経験が長い人は、プライドがどうしても邪魔をするんですね。それでも言い続けて、本人にも自分の言葉で語ってもらう。そうしていると、少しずつ行動が変わってきます。
────そうしたリッツ・カールトンのスタイルが合わずに、辞めていかれた方というのもおられますか。
もちろんいました。ごく稀でしたが、「外資系のホテルで一旗揚げよう」といった考えの人もいて、そういう人にはリッツ・カールトンの仕組みはしんどいんですね。こんな大変な思いまでして続けたくないと、去っていった人も何人かいました。ですから、仕組みを徹底していると、本当に思いがある人だけが残るということですね。
学歴や偏差値では、人の真価はわからない
────高野さんは、採用が非常に重要だとかねてから言われていますが、どのような点を重視して選考されていたのでしょうか。
リッツ・カールトンには、「QSP(Quality Selection Process)」という採用のシステムがあります。そこで見るのは、木に例えれば「根っこ」の部分。土から上の部分はだいたい見当がつきますし、偏差値を見ればどんな勉強をしてきたのかも分かります。しかし、偏差値が低いからといってその人の心が育ってないかというと、そんなことはなくて、ガキ大将タイプで面倒見がいいという人もいます。そうした学歴や偏差値からは見えない「根っこ」のところを探るのがQSPなんです。
────偏差値では、人の真価はわかりませんからね。そういった数字で見ているようではいかがなものかと、僕もいろいろな企業で言っているんです。
そういう企業が今、みな苦しんでいますよね。
────「根っこ」の部分とは、先ほど言われた「人のことを考える力」といった能力を見るということでしょうか。
そうです。選考ではその人の持っている「相手の立場になって考える力」を探ろうとします。例えば「ここ2週間であなたの大事な人のために何をしましたか」といった質問をして、日常生活の中で「人のことを考える力」をどれだけ発揮できているか、行動に移す力がどれだけあるかといったことを探るのです。
それは大げさなことでなくても、「友人が試験に合格したので、彼の都合が一番いい時間帯を選んでお祝いの電話をかけました」といったことでもいいんです。相手のことを考えるスイッチを、その人が日常の中でちゃんと持っているかどうか。例えば、笑顔の練習をしてくる人と心の中から自然に笑顔が出てくる人と、長い間こういう仕事をしていますと自然とわかるんですね。その人が持っている感性を、可能な限り探っていくのがQSPなんです。
ただ、どんなシステムも完璧なものはありませんから、採用した人の6割が期待通りであれば、とても高い確率です。残りの4割は、その6割に続く人に育ってくれればいい。そう考えています。
個人に置き換えてもそれは同じで、完璧な人間なんていませんよね。これはシュルツィに言われたことですが、人というのは性善説でも性悪説でもなく「性弱説」だと。人は本来、弱いものだということです。誰にでも強い部分と弱い部分があり、そのバランスの上で人は成り立っているわけです。ときどきバランスが崩れる瞬間があっても、それは人間の弱さが出ているわけですから、それも含めて受け入れればいいのだと。それがシュルツィの教えでしたね。
トップの愛情が、社員のホスピタリティを育てる

────ホスピタリティはトレーニングによって育てることができるけれども、採用ではやはり基礎的な能力の高さ、「相手の立場になって考える力」を重視しておられる。そしてその能力は、幼児期からの人との関わりの中で培われるものであるということですね。
そこなんです。私は今、子どもの教育にとても強い関心を持っているのですが、理由はそこにあります。例えば、「おばあちゃん子」や「おじいちゃん子」という言い方がありますね。以前は、甘やかされて育った子どもの代名詞のように使われていましたが、実は、祖父や祖母が身近にいる子どもの方が、人のことを考える力を持っている傾向があるのです。
理由はとても簡単で、「愛され度」が違うんです。徹底的に人から愛される時間を過ごした人は、ふとしたときに人の気持ちに添うことができる。それが、僕の最近の結論です。今、都会に暮らす子どもたちは孤独ですね。学校に行けば仲間がいるけれど、昔のように放課後に遊ぶということが少なくなって、みんな塾に行ってしまうでしょう。人と上手に付き合うことを学ばないまま、大人になってしまうんですね。
────僕も、親の影響は非常に大きいと常々感じているので、とてもよくわかります。社会に出てからも、上司や仲間といった人との関係性の中で人は成長していきますが、今はそうした関わりも少なくなっているように思います。上司が人としての在り方をきちんと指導して、ときには怒鳴りつけるくらいに関わっていくということがなくなってきているなと。そんな気がしているんです。
少なくなってきている理由は、トップが大家族の親になるトレーニングを受けていないことにあるのではないかと思います。今回、私の著書(『リッツ・カールトンと日本人の流儀』)でいくつかのすばらしい会社を紹介させていただいていますが、それらの企業には共通して、「会社は家、社長は親」という考えが根底にあります。ある会社の工場長などは、ふとした拍子に会長のことを「うちの親父さんは」と言われる。それを聞くと、ああ、ここは家なのだなと感じるんです。
トップは家長で、会社は家長が守ってくれる空間。その感覚が働く側にあり、トップもそうした感覚を持たせるように働きかけておられます。「地震、雷、火事、親父」と言うくらいで、昔の家長は怖かったでしょう。
────怖いけれど、愛情がありましたね。
そう、愛情ある怖さがトップにあるんです。そういった関係がなくなっていくのは、少し淋しい気がしますね。
100年先を見据えて、人とのつながりを育む
────この先、高野さんがおやりになりたいこととして、どのようなテーマをお考えですか。
ホスピタリティという生き方を提唱していくことを、ライフワークの一つとしてこれからもやっていきたいと思います。その一環として、『寺子屋百年塾』という学びの場を2010年の夏に長野県の善光寺で開講しました。これは研修会や講演と違って、参加者同士が学びを通じてつながり合うという、コミュニティづくりを目指す活動です。100年先を見据えて、今をいかに生きるかを考える機会をつくろうと、志を同じくする仲間が集まってスタートしました。3年目に入った今は、東京、北九州と開催地が広がっています。
もう一つ、農業のお手伝いも始めているのですが、現場にいると厳しい現実や問題がいろいろと見えてきましてね。巷には安価な食品があふれ、食べる人のことを本当に考えて、丁寧につくっているものが売れない。これだけものが豊かにある時代に、「食」が貧しくなっている。この矛盾を、何とかしたいと考えています。
────それは、ほかの産業でも同じことが言えるかもしれませんね。手間暇かけたものが本当はいいものなのに、その価値が認められない。そんなことが、あちこちで起こっているように思います。
そうですね。これは広い意味でいうと国家が持つべきホスピタリティだと思いますが、今は国家が機能していませんから、自分たちで解決していくしかない。そう思っているんです。
────日本には「おもてなしの心」というホスピタリティがあり、それは突き詰めれば「何をもって何をなすか」だということにもつながりますね。そうして一人ひとりが自分の使命を考えて生きることが、組織の強さにつながると改めて感じます。今日は貴重なお話をありがとうございました。

- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 経営改革は、実行する「現場の実態」を把握して、初めて実現する(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく、
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 高付加価値化実現の背景に「経営者の本気」と「社員の士気」(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 高付加価値化実現の背景に「経営者の本気」と「社員の士気」 - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)