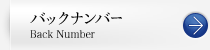OBT 人財マガジン

2012.08.08 : VOL145 UPDATED
-

医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター
理事長 亀田 隆明さん【既成概念に捉われないサービスを展開】
「人間にとって一番大切なもの」を追求する経営(前編)一般的に病院というのは、とかく規制が多く、患者や来訪者にとって居心地が悪い印象があるが、亀田メディカルセンターはハードもソフトも病院というより「ホテル」である。背景には、世の中のすべてのビジネスがサービス業化している現在、「医療もサービス業」という考え方がある。「高度な医療技術の提供」「病院施設の快適さ」についても特筆すべきだが、最も他と違う点が「患者と来評者に満足してもらうサービスの提供、ホスピタリティ」であろう。同院は"Always say yes!(患者の要望にはNOと言わない)"をモットーとし、更なるサービスの高度化を図っている。一方、多くの企業ではマニュアル等によって売り手側の「効率」を図ってはいるが、顧客価値への「効果」はどうか。競争環境が厳しくなる中で顧客離れを防ぐためには今一度、自社事業において最も重要なことを問いかけるべきなのではないだろうか。(聞き手:OBT協会代表 及川 昭)
-
[及川昭の視点]
どんな時代でも、どんな事業でも失ってはいけない普遍的に大切なものがあるように思う。
今回、訪問させて頂いた千葉県鴨川市の"医療法人亀田メディカルセンター"は、かなり前から、様々なビジネス誌等に「優れた病院経営の在り方」或いは「これからの病院のあるべき姿」等という内容で紹介されていた。
然しながら、今回、お会いして、私は、それは単なる"優れた病院経営"というレベルをはるかに超えて"人にとって一番大切なものを追求している組織"という捉え方の方がまさに当を得ていると実感した。これは、本当に大事になることと大事でないことを取り違えてしまっている我々日本人にまぎれもなく突きつけられているテーマではないかと。
企業経営という点で見ても、赤字の事業は、効率の悪い仕事は、止めるという一見合理的と思われる経営判断が、組織で本当は大事にしなければならないものを失わせやがて会社を弱体化させていく。

未だかつての成長市場時代の延長線上での経営と目先や短期的価値感に陥ってしまっている企業が非常に多い中で、まさに経営リーダーの賢慮さが経営の優劣を決するという思いを新たにさせられた時間であった。
聞き手:OBT協会 及川 昭
企業の持続的な競争力強化に向けて、「人財の革新」と「組織変革」をサポート。現場の社員や次期幹部に対して、自社の現実の課題を題材に議論をコーディネートし、具体的な解決策を導き出すというプロセス(On the Business Training)を展開している。 -
医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター(亀田総合病院・亀田クリニック) (http://www.kameda.com/)
亀田家は江戸時代・寛永の末頃より歴代医療を営む。法人としての発足は1948年。有限会社亀田病院を設立し、1954年に医療法人鉄蕉会(てっしょうかい)に改組。1964年から本格的に総合病院として発足し、千葉県南部の基幹病院として地域医療を担う。1985年には民間病院として全国初の救命救急センターとしての指定を、翌86年には医師の卒後教育を行う臨床研修指定病院の指定を厚生省(当時)より受ける。1989年には中長期計画(マスタープラン)を策定して、今後のあるべき役割を明文化。これに沿って1995年に外来専門の亀田クリニックを開院し、入院部門を中心とする亀田総合病院との機能分化を図る。2012年4月には亀田病院准看護婦学校(1954年開校)を源流とする学校法人鉄蕉館亀田医療大学を開設、同年8月には超高齢化社会に対応した新A棟をオープンさせ、時代に応じた高次医療サービスを追求し続けている。
亀田総合病院/診療科:33科、病床数:925床、亀田クリニック/診療科:31科、診察室100室、病床数:19床TAKAAKI KAMEDA
1952年生まれ。1975年、医療法人鉄蕉会理事に就任。1978年に日本医科大学医学部を卒業。1983年、順天堂大学医学部胸部外科教室大学院を卒業し医学博士号を取得。1985年に医療法人鉄蕉会 副理事長に、そして2008年に理事長に就任。財務省の財務総合政策研究所や財政制度等審議会の有識者メンバーなどの公職も歴任。
-
事業の二本柱を打ち立て、"良い循環"を生み出し続ける
────亀田メディカルセンターの取り組みは、優れた病院経営のあり方として注目されることが多いと思いますが、私どもはまた違った見方をしています。どんな時代でも、どんな事業でも、失ってはいけない普遍的に大事なものがある。ひと言でいえば"人にとって一番大切なもの"ということになるのかもしれませんが、亀田さんは組織全体でその価値を追求されていると我々は捉えているんです。これは、我々日本人にまさに突きつけられているテーマでもあると思います。私どもは、長い間、さまざまな企業と仕事をさせていただいてきましたが、昨今は、合理性という名のもとに儲からない事業や非効率なものはやめる、あるいは生産性追及のための徹底したマニュアル化等といったことを多く見聞きします。それらが結果的に何をもたらしているかといえば、働く人のモチベーションを低下させ、組織に疲弊感や停滞感を蔓延させています。これは経営トップが"賢慮"かそうでないか。この違いが非常に大きいと感じているんです。今日はそういった観点で、話をお聞かせいただければと思います。
お役に立てるかどうかわかりませんが、人口が3万5000人しかない田舎町に、医師が400名以上いて、職員も3000名近くいる。これは極めて稀有なことだと思います。特にこの千葉県は、人口当たりの医師の数が少なくて、全国で下から3番以上に上がったことが一度もないんです。南部の地域は亀田病院がないとどうにもならないでしょうし、東部は完全に医療が崩壊しています。
ですから、我々の使命の一つはこの地域の医療を守ることです。ではどうすればそれができるか。幅広い医療ニーズに応えるには、相当数のドクターが必要です。そのドクターたちに、やりがいを持ってここで活躍してもらうには、一般医療だけをやっていたのではダメなんです。優秀なドクターは志が高い人たちばかりですから、高度な臨床もやりたい、研究もやりたい。その欲求も満たさなければ成り立たないんですよ。
つまり、高度医療と両立させなければ、地域医療は守れないということです。もちろん医療者の教育も必要です。良い医療をやろうと思っても、人がいなければできませんから。人財そのものが我々の最大の商品ですので、"患者さま第一主義"と同じレベルで"職員第一主義"も大事。そう考えれば、当たり前のことをしているだけなんですけれどもね。
 *
*
(写真左)2005年竣工のKタワー。病室は全室個室でオーシャンビュー。コンシェルジュデスクも設置するなど、患者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を追求した病棟となっている。また同院では職員を"内部顧客"と捉え、内部顧客の満足度も重視。患者と職員の動線を完全に分け、働きやすい環境づくりにも注力している。
(写真右)Kタワーの霊安室。内装は、宗教色を排した清楚で明るいデザイン。"天国に一番近い場所"として最上階の13階に設置されている。────確かに理事長が言われる通りですが、当たり前のことが当たり前にできないということが、やはり多いように思います。例えば、地域医療を追えば高度医療はできない、といったように。
それは、問題の本質がわかっていないからではないですか。両方を追わずにうまくいっているケースはありません。向上心のある優秀な人たちは、常に高度な医療を追求します。追求できる環境があるからこそ優秀な医師が集まり、高度な医療とサービスを徹底するからこそ患者さまが集まって地域医療も充実する。この回転がなければ、ここで医療を継続することはできません。
ですから、我々にとって一番のポイントは"サステイナブル(持続可能な)"であるということです。そのためには、常に前進する組織でなければならない。自転車が止まったら倒れるように、一度回転が止まれば必ず落ちていくんです。
──── 止まった回転を再び動かすのは、大変なことですからね。
そう、グループ全体では4000人の組織ですからね。自動的に回り続ける仕組みでない限り、無理なんですよ。
積み上げではなく逆算の発想で、経営の舵を切る
────そうした取り組みは、結果が出るまでにかなり時間がかかるかと思いますが、今日の病院のあり方に向けて、いつ頃から経営の舵を切られたのでしょうか。

今から約30年前に、この病院に一流の心臓外科のチームをつくったことが始まりです。私自身が心臓外科医で、順天堂大学の鈴木章夫先生という新進気鋭の心臓外科医のもとで学んだのですが、1983年に鈴木先生の了解を得て、順天堂の優秀な医療スタッフを亀田に招聘したんです。私が30歳のときのことです。
そうして医療環境を整えたうえで、フロリダから外山先生という心臓外科医(現・心臓血管外科顧問 外山雅章医師)──浅田次郎の小説『天国までの100マイル』のモデルにもなった方ですが──を招聘し、心臓血管外科部長に就任してもらった。そういうことを、いきなりやったんです。
ただし、患者さまの半数以上を首都圏から集めないと高度医療は成り立たない。最初からそうしたことは考えていました。そして、2年目か3年目には「難しいケースは亀田で」と大学病院から患者さまが送られてくるようになり、診療の7割は都内を中心とした大学からの紹介になっていました。そこから、高度医療と地域医療を両立する回転に持っていったわけです。
────こうした前例がないことというのは、うまくいくかどうかが非常に不透明な中で、なかなか一歩踏み出せないというのが普通だと思います。しかし、理事長は高度医療を確立すれば首都圏から患者を集められるという自信を、当初から持っておられた。だから、思い切って進めることができたということでしょうか。
ええ。日本で最高の医療を提供すれば可能だと、そう思いましたのでね。ただし、1番でなければいけない。2番ではダメだと思いました。だから、夢中で駆けずり回って一騎当千の人財を集め、チームを組んだのです。当初は私も心臓外科医としてやっていましたが、そこに「外山先生のもとで学びたい」と、今をときめく若手のエースたちが研修医として入ってきた。そうなると、私なんかがいたら邪魔になりますからね。彼らが伸びる妨げになると思って私は臨床から退き、自分が得意とするコーディネーションに専念したわけです。
そして、この回転をいろいろな診療科に広げていきました。レベルの高い科が一つあると、ほかの科にもプレッシャーがかかります。いろいろな科が常に高みを目指すようになって病院全体のレベルが上がり、そこにまた優秀な人が集まる。この回転が始まるんです。
────最初に心臓外科のチームをつくられたときに、既に今日の病院のありようを描いておられたのですか。
ある程度のイメージはありましたね。いけると思いました。といっても、今の状態を詳細に考えていたわけではありませんが、例えばそのときの心臓外科や脳外科は、現在の亀田病院に十分匹敵するレベルでしたから。
また、当時はこの地域に救急病院などもありませんでしたので、1985年には民間初の救命救急センターを設置し、その翌年には医師の卒後教育を行う臨床研修指定病院に厚生省(当時)から指定されました。地域の一病院が、高度医療を手がける総合病院にあっという間に生まれ変わっていたんです。
普通なら、3万人ちょっとの町にこういった病院をつくるといえば、どう考えてもおかしいと思いますよね。でも時間はかかりましたが、現にこの病院がここにできている。「3万人だから無理だよね」と諦めていれば、今の亀田病院はなかったでしょう。どうすればできるかを一生懸命に考えて、常にカッティング・エッジ(最先端)を走り続けてきた。その結果として今があるんです。
プロにとって最高の環境とは、進むべき道を自由に選べること
ただ、医療の世界は特殊な部分もあって、うちで一生懸命育てた人が外に出て行って活躍しているケースも多いんです。これもまた良しなんですね。例えば、先日の天皇陛下の心臓手術を執刀した医師(順天堂大学医学部心臓血管外科教授・天野篤医師)は、うちの後期研修医だったドクターです。彼はここで勉強した後にいくつかの病院を経験し、順天堂大学の教授に就任しました。ほかにも、ここから巣立って活躍している人はたくさんいますよ。
────それは亀田病院にとっては戦力の喪失ではないですか。
もちろん一時的にはそうです。あちこちに引き抜かれて、トップクラスの医師が4人ぐらい一度に移っていく年もありますが、そうなると立て直すのに1、2年はかかります。若くてちょうどこれからという医師が、スカウトされることもありますしね。しかし、大学でも育てられない人財がここで育つということが、また新しい優秀な人たちが集まる要因にもなるんですよ。
────結果的に良い循環になっていくということですね。
そうですね。もちろん、ここでのモチベーションを高めてもらうために、さまざまなインセンティブを工夫していますが、この病院から羽ばたいて行けるということも、大きなインセンティブなんです。ですから私たちは囲い込みもしないし、むしろ応援する。ちょっと独特かもしれませんね(笑)。
────ある経営者の方がこんなことを言われていたのですが、何かを決断するときは、それが将来良い循環につながるか、悪い循環になるかを考える。将来の確証はなくても、どのような循環をたどるかは考えるべきだと。こう言われたことに今のお話は近いように思いました。
我々は何十年とやってきた中での現実として、こういう循環にできましたのでね。ただ、医師のキャリアパスには、さまざまな道があります。大学病院の教授になる人ばかりではなく、ここでリーダーシップを発揮するようになる人もいれば、海外に渡る人もいますし、自分で開業する人もいる。それを"こうでなければいけない"と、型にはめることはしないということなんです。
社会になくてはならない意味を、手がける事業に見いだせるか

────看護師の方々については、定着率はいかがですか。
先ほどもお話したようにこの病院は教育機関でもありますので、看護師も医師と同様に回転は速いです。今年でいえば、4月の入職者は約300名でそのうち医師が80名、看護師が95名。中途採用も含め毎年100人以上のナースが入り、それに近い人が出ていきます。平均在籍期間は5、6年。うちに限らず、大学病院も同じくらいですね。
これはやむを得ない部分もあるんです。看護師の業務は3交替もしくは2交替、つまり夜勤があるわけです。ですから、結婚すると家庭との両立が難しい。お子さんがいたらまず無理でしょう。22歳で看護師になったとして、結婚年齢が28、29歳くらい。それまでの間が雇用期間になるわけです。もしくは子育てが終わった方に、もう一度復帰してもらうか。
ですから、今後は育児と両立できる環境を整えることが非常に重要になります。ただこれも難しいところがあって、24時間の保育室を設けても、やはり「自分の手で育てたい」という母性本能にはなかなか勝てないんですよ。この問題は医師も同じです。特に産婦人科は女性の医師を希望する患者さまが多いですから、今は専門医の認定を受ける医師の7割が女性です。しかし、その人たちが10年後にお産を手がけている確率は10%以下。結果として、残り3割の男性ドクターに負担が集中し、疲弊して医療崩壊が起きる。これが現実なんです。
ではどうすればいいかといえば、絶対数を増やすことが得策ですね。そこは我々も力を入れているところです。
────病院を維持されるだけでも、大変なご苦労があることを改めて感じますが、今日に至るまでの中で一番苦労されたことはどのようなことでしたか。
常に先行投資を続けてきましたので、ファイナンシャルな壁は常にありましたね。なかでも決定的な先行投資になったのは、1990年から開発を始めた電子カルテです。パソコンも普及していない時代に、世界で初めて、世の中にないものにトライしたんです。前例のないことをやると困るのは、まず関連する法律がないんですね。カルテは公文書ですから5年間の保存義務がありますが、電子カルテは公文書なのかどうか、法律のどこにも書いていないわけです。厚生省に尋ねると、「ないものに法律を作りようがないから、とにかくやってみてくれ」と。電子保存が正式に認められたのは、それから2年後のことでした。
その間は、仕方がないから電子カルテをすべて出力して保管するという、紙と電子の二重運用をしましてね。倉庫のスペースも、運搬要員の人手も膨大にかかりました。しかも、初代の電子カルテは稚拙極まりないもので診察に倍の時間がかかり、結局一からつくり直すことになって何十億円かの赤字を出しました。それを盛り返すのは大変でしたね。でも、このことがあったので電子カルテが世の中に出回り、当たり前のように使われるようになったんですよ。
────そうした前例のない挑戦を続けていかれる中で、何が理事長の支えになったのでしょうか。
やはり、この病院が地域にとってなくてはならない存在だということですね。そして、日本の医療の一つのモデルでもあるということ。私は、政府の財政制度等審議会などにも有識者として参加しているのですが、政策の根幹の議論をするときに、こうしたことをやっている者でなければ言えないような意見も言えますのでね。
といっても、あまり難しく考えたことはなくて、誰でも人の役に立てるならやりがいがあるじゃないですか。たまたま、そうしたことができる立場にいるというのは、幸せなことだと思います。大変といえば大変かもしれないけれど、その分大きな喜びをもらえますから。それは偽善でも何でもなくて、自分がやりたいからやっているわけでね。それが一番の根本でしょうね。
医療が果たす役割を突き詰め、亀田理事長は道なき道を歩んでこられました。「常にカッティング・エッジを走り続ける」というその姿勢に、どのような信念が込められているのか。後編では亀田理事長の経営観と、今後の医療への思いについてうかがいます。
*続きは後編でどうぞ。
既成概念に捉われないサービスを展開「人間にとって一番大切なもの」を追求する経営(後編)

- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 経営改革は、実行する「現場の実態」を把握して、初めて実現する(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 企業の競争優位性は結果指標ではなく、
それを生み出す組織の強さ、社員のモチベーションに規定される(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 高付加価値化実現の背景に「経営者の本気」と「社員の士気」(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 高付加価値化実現の背景に「経営者の本気」と「社員の士気」 - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)