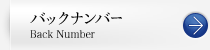OBT 人財マガジン

2009.11.11 : VOL79 UPDATED
-

株式会社ティア
代表取締役社長 冨安 徳久さん
日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社の組織づくりと人づくり(前編)
人はみな、いつかは『最期』を迎えます。しかしそれは、できれば考えずにおきたい『縁起でもないこと』。葬儀のときを迎えても、費用を細かく確認するなどのお金の話は『はしたないこと』だとされ、葬儀社の言い値がまかり通る風習が長くはびこっていました。そんな葬儀業界に一石を投じたのが、名古屋を中心に葬儀会館を展開するティアです。『目指せ──日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社』をスローガンに、葬儀料金の明細をホームページやチラシで細かく公表し、業界平均の半額以下という驚異的なプランを提示。社員はみな会社の信条を記した『クレド・カード』を所持し、1つ1つの葬儀に心を込めて故人の旅立ちをおくる。隅々にまで理念が浸透した組織は、どのようにして生まれたのでしょうか。裸一貫、ゼロからティアを立ち上げた代表取締役社長 冨安徳久さんに伺いました。
-
株式会社ティア ( http://www.tear.co.jp/)
1997年設立。社名の意味は『涙』。葬儀会館『ティア』を展開し、葬儀施行を手がける。料金は、ドライアイス1回分の費用に至るまで詳細に公開する明朗会計。入会金1万円のみで、月々の掛金や年会費は一切不要な『ティアの会』を組織し、会員には特別価格でサービスを提供する。旧来の葬儀業界にはない独自のビジネスモデルが消費者に支持され、会員数は累計で13万人を超え、会館数は36館にまで拡大(2009年10月現在)。2006年に名証セントレックスに上場、2008年に名証二部に指定変更。フランチャイズ事業も手がけ、葬儀会館『ティア』の全国展開を目指している。
企業データ/資本金:5億円8075万円、従業員数/203名(連結、2009年7月現在)NORIHISA TOMIYASU

1960年生まれ。1979年、18歳のときに、短期アルバイトのつもりで始めた葬儀の仕事に感動し、大学入学を辞めアルバイト先に入社。1981年に愛知県にある大手互助会に転職。1994年に独立を決心し、1997年にティアを設立。著書は『ぼくが葬儀屋さんになった理由(わけ)』(講談社刊)、『ありがとうすべては感動のために―「命の尊さ」を知る!究極のサービス業・ティア流葬儀ビジネス』(綜合ユニコム刊)、『1%の幸せ あなたのココロを磨く45の気づき 』(あさ出版刊)など。
-
業界で初めて、『適正な葬儀価格』を打ち出す
────平均費用が200万円とも300万円ともいわれる葬儀業界において、御社の平均単価は119万6000円。業界の常識を打ち破る価格を打ち出された背景をお聞かせください。
当社の価格設定は、『激安価格』や『価格破壊』だとよくいわれます。12年前に会社を設立した当初から、テレビや新聞、雑誌などマスコミにはよく取り上げていただいているのですが、みなさんそうおっしゃる。しかし、私はその度にお伝えしているんです。「当社は価格破壊をしているわけでも、激安価格でご提供しているわけでもありません。業界で初めて、適正な価格をご提示しただけなんです」、と。
例えば、ご遺体に添えるドライアイス。10キロで1万円が、この業界の平均価格です。中には1万5000円という価格をつけているところもありますし、10キロという量すら明記していなところもあります。このドライアイスの仕入れ値がいくらか、ご存知ですか? 1キロ150円です。それを1万円で売っているんですよ。
これはほんの一例で、これまでの葬儀業界では、こういった明細すら提示されないことも珍しくありませんでした。どんなデパートに行っても値札のない商品は一つもないのに、こと葬儀に関しては値札のある商品が一つもない。消費者も葬儀の値段を細かく確認することをタブー視してきましたし、業界も価格をブラックボックス化してきたわけです。
それに対して、サービスにすべて値札をつけ、チラシにも価格をハッキリと提示して、基本的なものはすべて『祭壇セット』としてセット価格にしましょう、と。当社は、そのことをやっただけなんです。なぜ常識破りの価格にできたかといえば、本当の原価はもっと安いから。これまでの価格は、業界が勝手につけていただけなんです。
今では、当社が名古屋地区で15%の占有率を持つまでになりました。その結果、この地区の葬儀の平均費用は、約300万円といわれていたものが、約250万円にまで下がりました。当社の平均価格はさらにその半額以下、119万6000円です。それでも、売上高経常利益率は7.1%(※)、総資産経常利益率は8.3%(※)。この価格でやってもきちんと利益が出るんですよ。
※平成20年9月期実績
経営者は『公憤』を持たなくてはならない

葬儀業界の価格のあり方に疑問を感じるようになったのは、2番目に勤めた葬儀社で、25歳で店長になったときのことです。店長になると仕入れ価格がわかるようになります。その安さには、驚きました。こんなに原価が安いものを、なぜ200万円、300万円で売るのか。それが私には理解できませんでした。
決定的な問題意識を持ったのは、その5年後のこと。その年に会社から、「今後、生活保護者の葬儀は扱わない」という方針が発表されたんです。当時、会社が請け負う葬儀全体の約3%から5%は、生活保護の方々の葬儀だったんですね。100件のお葬式があれば、3件から5件はそういった方のお葬式。こういった葬儀には、市町村によって金額に多少の違いはありますが、葬儀扶助といって20万円ほどが自治体から支給されます。その費用でもって病院にお迎えに行き、生活保護の方の最期をおくるということをしていたわけです。
20万円といえば、人件費も入れると収支トントンか、やや赤字という金額です。でも残りの9割以上の葬儀では、いってみれば暴利を得ているわけですから、全体の3%や5%くらいは赤字でも、生活保護の方々を助けてあげればいいじゃないですか。それを会社は、「生活保護者の葬儀は請けるな」という。
それを聞いたときは心底驚いて、何を言ってるんだ、と思いました。最初に勤めた葬儀社で教わったのは、「人の死を、分け隔てしてはいけない」ということです。ご遺族がお1人でも100人でも、お金持ちでもそうでなくても、人の命の最期に大きな悲しみがあるのは同じ。差別をしてはいけない、と。それが、この葬儀ビジネスの揺るぎない根幹だと私は思っていたんです。
冷静に考えてみれば、人の死と悲しみを持って、売上や利益を追求するビジネスをさせていただいているのは、葬儀社だけです。命の最期に接するビジネスに関わる者として、亡くなった方を尊ぶ気持ちを持ち、ご遺族の悲しみをきちんと受け止めるのは当然のこと。そう考えると、相手によって差別するというのは、許されないことなんです。
しかし、会社は「生活保護者の葬儀は断れ」という。「うちは、全国で10本の指に入る大手互助会だ。お金のない末端の人たちの葬儀は、個人の葬儀社に任せておけばいい」と。そこで私は、店長会議で経営幹部に反論したんです。ほかの店長たちにも事前に相談したら、「会社のあの方針はないよな」と、みんな私に同意してくれました。
ですから、「反対しても会社が聞き入れてくれなかったら、みんなで賛同してくださいね」と店長たちにお願いして、今言ったような話を経営陣にしたんです。「人の死をビジネスにしていいのは、葬儀社だけですよね」と。「もちろんボランティアではないということは理解していますので、ほかの葬儀で売上と利益はきちんとあげます。ですから、生活保護者の葬儀もお手伝いさせてください」と。そうしたら、「その方針はもう決まったことだ」と、雷が落ちるくらいに幹部に怒鳴り散らされまして。店長たちはといえば、みんな黙って下を向いている。誰も顔を上げないんですよ。
────話が違いますね。
そう。ただ、考えてみれば仕方がないんですね。当時、店長の多くは40代の年輩の方々でしたが、私は30歳。若かったこともあり、一族郎党の経営幹部に逆らうのがどういうことか、考えたこともありませんでした。でも聞けば、過去に一度、親族に逆らった人がどこかへ飛ばされてしまったらしいんですね。だからみんな、一族が決めたことには逆らえないわけです。
そのときです、業界のあり方に疑問をハッキリと感じたのは。それまでも、遺族の方々にはとても感謝される仕事なのに世間では偏見の目にさらされて、「人の死で飯を食っているのか」とか、「祭壇なんて、あってないような値段なんだろう」とかね。いろいろと言われてきたことも思い出されまして。この社会性の低さの原因は、閉鎖された業界にあるということがよくわかりました。これは何としても業界を変えなくてはいけない、と。そこから、独立を考えるようになったわけです。
私は、商売には『怒り』が必要だと思っているんです。誰かが歩いた道を歩くのであれば、『怒り』なんてものは、いらないかもしれない。しかし、道なき道を切り開くのは、ゼロから1を作るということ。これには『怒り』が必要です。
では、『怒り』とは何か。『公憤』という言葉がありますね。故・松下幸之助さんの『指導者の条件』にはこうあります。「指導者たる者、いたずらに私の感情で腹をたてるということは、もちろん好ましくない。しかし指導者としての公の立場において、何が正しいかを考えた上で、これは許せないということに対しては大いなる怒りを持たなくてはいけない(※)」と。
※「指導者の条件」(松下幸之助著 PHP研究所刊)より
資産家の息子でもなければ、葬儀屋の息子でもない私が、独立のリスクを負ってでもティアを創業したのは、葬儀業界に一石を投じなくてはならないという思いから。適正な価格を打ち出す葬儀社として業界基準を作り、セレモニーブランド・ティアを作り上げてやろう、と。その使命感に駆られたのは、この『公憤』という怒りからなんです。
『日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社』を作る
その後、37歳で独立したときに最初にしたのは、経営理念を自分の言葉で書き表わすことでした。『目指せ──日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社』というスローガンです。なぜそうしたかといえば、会社を創業するのは理念を実現するためだから。理念は、私の生涯のスローガンです。
もちろん企業ですから売上や利益も追求しますが、それは経営者であれば当然のこと。そうでなければ、大切な資金を投資してくださった方々に顔向けができません。でも、そこに理念がなければ、本質がずれていってしまいます。このところ企業の不祥事が続いていますが、ああいったことは完全に経営者の責任。売上や利益だけを追求するから、そういうことが起るんです。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
理念を創りあげた当時のことを、冨安氏は自著「ぼくが葬儀屋さんになった理由(わけ)」の中でも次のように語っている。
「新会社設立のためにやらなくてはいけないことが山のようにあったけれども、中でも最初にやった重要なものは理念作りであった。
(中略)
目指すは「売上・利益の日本一」ではなく、どこの同業他社よりも「ありがとう」と感謝される葬儀社になりたかった。それと企業の旗印として、会社が存続する限り、変わることのない想いを「生涯スローガン」として言葉にした。それが『目指せ──日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社』である。
──「ぼくが葬儀屋さんになった理由(わけ)」(講談社刊)より
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------経営理念をつづるときに大事にしたのは、わかりやすい言葉で表現することです。社員と共有するためには、難しい言葉で語らない。『単純化戦略』はとても大切です。
さらに、理念をかみ砕いた『クレド・カード』も作成し、社員に配布しました。『クレド』はザ・リッツ・カールトン ホテルが有名ですが、リッツ・カールトンが日本で初めて大阪の梅田に進出した97年に当社は始まったんです。その雑誌の記事に、「リッツ・カールトンのモットーは、『We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen(紳士淑女をおもてなしする私たちもまた紳士淑女です)』だ」とあるのを読んで感動しましてね。お客さまにただ仕えるだけの存在ではダメだ、ということです。これはすごいな、と。
さらにリッツ・カールトンには、「理念や信条をまとめた『クレド・カード』がある」と書いてある。今でこそリッツ・カールトンを紹介する書籍が多く出ていますが、当時はまだそういったものがない時代です。私は、すぐにリッツ・カールトンに泊まりに行きました。「『クレド・カード』をください」というお願いは断られましたが(笑)、見せてもらうことはできましたのでその場で大方を頭に入れ、それを参考にティアの『クレド・カード』を作成したのです。
設立5年目に組織が急拡大。求心力を失う危機を迎える
────しかし設立5年目に、理念が組織内に伝わらないという事態を経験されたと、ご著書で拝見しました。会館を5店舗から一気に10店舗に増やされ、組織が急拡大したことが原因だったとか。その状況を、どのようにして打開されたのでしょうか。

創業時には、『毎年2店舗ずつ会館を増やし、10年で20店舗にする』という事業計画を立てていました。そして2年目、3年目は計画通りにオープンできたものの、4年目は27人の地主さんに交渉してすべて断られましてね。それが、5年目にたまたま話が重なって、一気に5店舗から10店舗に増やすことになったんです。それに伴って急きょ社員募集もかけ、初めて経験者を何人か採用しました。基本的には同業他社の出身者は入れたくなかったんですが、出店の必要に迫られて採用したわけです。
────経験者の採用を避けるのは、なぜですか。
同業他社に何年かいると、仕事の手を抜くということを覚えてしまうんですよ。当時応募してきたのは、経験がまだ3、4年の若手でしたので、他社のやり方にそれほど染まっていないかなと思って採用したのですが、結局のところは2、3年もいれば、もう横着を知っているんですね。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当時を、冨安氏は自著でこう振り返る。
「会館が増えるに従って、『ティア』の何かが違ってきたことに気がついた。遺族のアンケートや施行社員の報告書から、遺族との心の触れ合いが伝わってこないのだ。店長会議でも売上と利益の無味乾燥な話だけしか出ない。
(中略)
七、八館に増えた頃から、すでに会館ごとに方向性のばらつきが見えはじめ、『このままではダメになってしまう』とまで思った」
──「ぼくが葬儀屋さんになった理由(わけ)」(講談社刊)より
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------また、社員数が倍になりましたから、教育係の社員が全員を見渡せなくなり、建物が5店舗から10店舗に増えたことで、物理的な物事をこなすので精いっぱいだったという事情もありました。
この経験で実感したのは、やはり『人』がすべてだということです。建築に例えれば、建物が高くなればなるほど、基礎は深く掘りますね。会社も同じで、組織を大きくするには、それだけ理念という基礎をしっかりと共有する必要がある。それまでも共有する努力はしてきたつもりでしたが、実際には足りなかったということなんですね。
これはもう忙しくても何でも、理念を徹底的に再教育しようと。当時、私が講師を務める90分の社内セミナーを月に16回は開いたでしょうか。それまでも、葬儀がない友引の日に社員を集めて理念教育のセミナーを開いていたのですが、友前(ともまえ)といって、友引の前日の夜にも開催するようにしました。友前はお通夜がありませんから集まりやすいんです。社員には夜に来てもらうことになりますが、残業代を払ってでも研修を受けてもらおうと。そのようにして、われわれがなぜティアという会社を立ち上げたのか、その根底にある考え方や物の見方、捉え方を、一字一句ひも解いて、再教育をしていったんです。
────その過程では、辞めていかれた社員の方もいらっしゃったそうですね。
主に経験者が退職していきましたね。横着を知っている者が排除され、楽な仕事を求めるほかの社員も一緒に辞めていき、結果として社員がものすごく精査されました。今、残っている幹部は、当時の苦労を一緒に乗り越えてきた者ばかり。ハードな経験でしたが、そのことによって、人を育てることがいかに大切か、管理体制をしっかりと構築して組織力を強化することがいかに大切かということを学んだのです。
各会館の支配人を統括する、マネジャーのポジションを作ったのもこの時期です。自分たちの職制や職域も、日々もまれる中で理解していきました。例えば、社員の誰かが休んだからといって、支配人が代わりに葬儀についたのでは、会館全体の運営を見ることができなくなります。支配人が病欠したからといってマネジャーがその会館に入り込んで仕事をしていては、複数の会館を統括することはできません。誰かが欠けたときにどうするかまで考えておくのがマネジメントなんです。そういったことを現場で学んできた社員たちが今、部長や事業部長になって、組織を支えてくれているんです。
急成長期の危機を乗り越えたティアは、その後も右肩上がりの成長を続けます。現在の社員数は200名超。組織が拡大しても強固な一枚岩であり続ける秘けつはどこにあるのか。後編では、冨安さんの組織観、人財観を伺います。
*続きは後編でどうぞ。
日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社の組織づくりと人づくり(後編)

- 株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
専務取締役 矢部 輝夫さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
企業改革を阻む制約をいかに克服するか(前編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(後編) - 千葉夷隅ゴルフクラブ
総支配人 岡本 豊さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
見えざる資産を競争優位にするために必要なこと(前編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(後編) - 七福醸造株式会社
代表取締役会長 犬塚 敦統さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
人が気づき、変わる瞬間とは(前編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(後編) - 株式会社キングジム
代表取締役社長 宮本 彰さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
知というアイデアを製品化し、利益に結びつける組織とは(前編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(後編) - 東海バネ工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 良機さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
やること、やらないことを決める
競争優位を明確にすることは、社員育成にもつながる(前編) - 人とホスピタリティ研究所所長
前リッツ・カールトン日本支社長
高野 登さん - 【事業で差別化しうるのは唯一人財のみ】
成熟化社会は、ホスピタリティが鍵となる(後編)