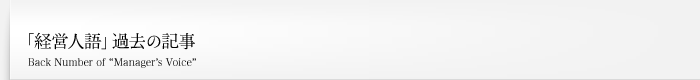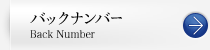OBT 人財マガジン

2012.07.25 : VOL144 UPDATED
-
子会社とは一体誰のものか?
昨今の日本企業は、グループ経営における子会社を「戦略的ポジション」或いは
「重要ポジション」等といったところに位置づけ、対外的にもそのようなメッセージを発信している。
然しながら、現実的には親会社と子会社の関係は概ね以下の通りの実態であろう。
・親会社の事業の中で付加価値の低いものを子会社に移管してコスト低減を図る。
・親会社の組織構造のスリム化、或いは事業効率向上のため余剰人員を子会社に出向、
或いは転籍させて企業体質の強化を図る。
・事業構造の再編等により本業とはかなり性質の異なる事業を遂行するために当該業務を
子会社に担わせる。
・社長以下、経営陣や管理職クラスも常に親会社から派遣された出向者や転籍者の人達で
占められ、定期的にこのサイクルが繰り返される。
・同じ仕事をしながらも、親会社から派遣される人間と子会社生え抜きの社員との間に待遇や
給与格差がある。
・親会社の連結経営という名の下に組み込まれているので、子会社独自の利益計画が
立案出来ない。
・親会社とは、事業の性格も特性も全く異なるにもかかわらず、制度や仕組みは親会社と
同種のものを多少表現を変えた形で導入され管理手法として使用される。
また、親会社からの出向者の資質は、優秀な人材というよりもどちらかというと窓際や親会社では
使えない人材が送り出されてくるというのが一般的である。
上述のような実態は、すべからく子会社の自律性や高い業績を上げるための状況づくりを
親会社自体が阻害しているのに等しい。
これが本当に「戦略的ポジション」或いは「重要なポジション」という位置づけといえるのだろうか?
この結果、子会社の組織能力やスキルは、極めて狭い範囲内での状況対応能力にとどまって
しまい具体的には,"いかに早く"、"いかに安く"、"間違いなく""効率よく""従順に"等々に代表される
いわゆるHOWに関する能力やスキル等は培われるものの、"将来の方向性"や"自社の
成長シナリオの構築"等というWHATといった領域となると甚だ弱い。
要は、経営ではなく業務管理や作業領域のレベルを遂行しているということである。
一方で、多くの親会社は、自社の子会社を"提案力に欠ける""親会社依存的で自律性に
欠如している"等といった評価は汎用的なものであろう。
そして、子会社の業績が低迷すると親会社はその業績不振を、子会社の経営陣、或いは社員の
能力や意欲不足と決定づけ責めるのである。
子会社自らが主体的に業績改善の努力をしようとすれば、いい条件で優秀な人材を採用
しなければならない。または親会社の管理下から離れ、自律的な経営を志向することが不可欠と
なってくるが、これらの施策は親会社の不快感を増幅させていくのである。
親会社の意向に従って経営を行うことは、子会社の成長や競争力の強化には決してつながらず、
親会社の言うことに素直に従うという選択は、子会社を弱体化させグループとしての戦略的
意味合い等からも程遠くなってしまう。
結果として、子会社の企業体質はますます脆弱化し、親会社の庇護がなければ企業として
1人立ち出来なくなってしまう。
20世紀を代表する経済学者である米国シカゴ大学のミルトン・フリードマンが"政府が市場に対して
規制や政策的介入は控えるべきである。経済活動の自由度を最大限に認めることで市場のパワー
は向上する"と主張している。
制約や規制、そして管理・監督といったものは、管理する側の"特殊利益"にしかすぎない。
この特殊利益は、それに従うもののみならず、多くの大事なものを喪失させてしまうということである。
フリードマンの主張が優れているのは、"だからといって何でも市場に任せればいいというステレオ
タイプの市場主義ではなく、市場のパワーや活性化を促進するためにはどのような制度がキー
となるのか"ということである。
フリードマンの主張は "戦略的な子会社""競争力のある子会社"として成長させるためには、
管理する親会社の特殊利益ではなく、親会社として"どのような関連会社政策"を行うべきかという
本質論を示唆している。
もうひとつ重要なことに、上述のような親会社、子会社の関係において子会社の生え抜き社員の
主体性やモチベーションは向上するのだろうか?
一生懸命頑張っても将来は見えている親会社の枠の中で、親会社の政策しか存在しえないという
現実は、"我々は,ただ親会社のためにだけ仕事をしている"という被害者意識をも蔓延させてしまう。
結果的に、親会社や出向経営者、管理者の考え方等に必要以上に適応していこうとする姿勢や
予定調和的価値観に陥ってしまい、自分達の頭で考え自分達で答えを出すといった主体性に
欠如した、極めて状況依存的な人材の集団と化してしまう。
そして"現在も将来も""生きるも死ぬも"親の都合次第になってしまう。
これで、本当に想定外の変化が生じるこの厳しい競争時代に対応しうるのだろうか?
そこには、企業グループ経営における賢慮さ等は全くといっていいほど感じられない。
例えば、古河電工とシーメンスの合弁会社である富士電機の電話部門が分離独立して子会社として
設立された富士通は、日本を代表するエレクトロニクス企業となり、その富士通もファナックや
ニフィティ等の数多くの優良子会社を輩出している。
現在も親会社である富士電機と富士通およびその系列会社は、互いに筆頭株主、役員を相互に
出し合う等同等の取引・パートナー関係、共同で新会社を設立する等兄弟会社のような親密な
関係が続いている。
親会社としていかなる関連会社政策を行うことが、子会社の成長や強さにつながるのかという
一つの証左であろう。
子会社とは株主である親会社だけの所有物なのかという本質論に立ちかえって考えるべきであろう。
子会社にも、親会社と全く同様にたくさんの世界や様々な人達の人生が存在するということを
忘れてはならない。
On the Business Training 協会 及川 昭