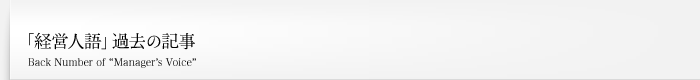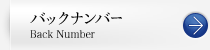OBT 人財マガジン

2012.01.11 : VOL131 UPDATED
-
優位性とは、誰でも出来ることを
誰にも出来ないレベルで徹底してやり抜いて始めて築けるもの!企業経営を考える際に考慮しなければならない要素は「競争」であり、特定の産業を除けば、ほとんどの企業は今非常に激しい競争環境の中に置かれている。厳しい競争の中で利益を上げるためには、当然のことながら競合他社との明確な違いがなければならないし、それにもまして、その違いを支持する一定の顧客が存在しなければならない。その違いが、競争相手とは明らかに異なる差別化となり特定顧客から「選ばれる価値」となりそれが競合他社に対する優位性として働く。また、差別化は、単に一時期の短い差別化であってはならない。競争相手が容易には追いつけないような、長期的に維持可能な差別化が望ましい。だから、単純な価格差別化はしばしば拙劣な戦略である。
価格を下げるだけなら、競争相手も利益を犠牲にすればすぐに追いつける。もし価格差別化に訴えようとするなら、価格差が十分に大きくて、しかも価格低下の背後に、十分すぎるほどのコストダウン努力があるものでなければならない。価格を武器にした戦いは、体力勝負の消耗戦であり自滅への道である。差別化とは換言すると、「際立つ」ことである。差別化している、際立った違いを出していると考えている企業の中には、「できる」という思い込みで、実はそれほど競争優位につながらないことを空しくやっている企業はことのほか多い。「できる」と「優位」とは明らかに違うのである。なぜその違いに気がつかないのだろうか。その理由。① 「明らかな」差がなければ、顧客の目を大きく自社の方へ向けることはできないということを忘れがちである。差別化をするのは競争の激しい市場では大変である。少しの差をつけるのにも努力がいる。その努力を考えると、「できる」ことは「優位」につながると思いたくなる。しかも、自分たちのもっている能力は少しでも意味があると思いたい。だが、顧客に本当にアピールできるためには、「明らかな差」でないとだめなのである。この誤りは、「企業勝手のちまちました差別化」の落とし穴、と言えるだろう。② 優位かどうかの最終判断者が顧客であることをつい忘れている。専門家の立場ではこれだけの差が「明らかにある」と思えても、それが顧客が望むような差でなければ、競争優位の源泉としては意味がない。いくら技術的にはすばらしい製品差別化だと開発技術者には思えても、顧客のニーズのポイントをついたような製品差別化でなければ、顧客には評価してもらえないのである。これもまた、差別化に必要な努力の大きさについ目を奪われて、「できる」ことを「優位」と錯覚している例である。この誤りは、「売り手本位の見当違いの差別化」の落とし穴、と言えるだろう。③ 競争優位を考えるあまりに、競争相手の動きにばかり注意を払い、肝心の顧客のことを忘れてしまうことである。真の「優位」とは顧客の心をつかむ優位なのに、競争相手との差別化が「できる」ことに注意がいきすぎる。いわば、競争に振り回されてついつい顧客のニーズ本位の考え方ができにくくなるのである。市場には顧客と競争相手と、両方いる。本来のターゲットは顧客であるのだが、それを勝ち取るために競争相手の上をいこうとばかり懸命になり、結局は顧客のことを忘れてしまう。「極立つ」ためには、どの土俵で戦えば、自分たちは持続的な差別化が可能なのかを冷静、かつ客観的に見極めること、そして数多くの選択肢の中から、自分たちが生み出すべき差別化された価値とは何かを決めることが経営の本質ではないだろうか。自分たちの「戦う土俵」を見極め、絞り込むこと、そしてそこにフォーカスすることが強さとなり、ビジネスの世界では、それがとても大事になる。然しながら、今日の環境下で優位性を構築することは並大抵のことではない。そのために一般的には、優位性を持っている企業は、何か特別のことをやっていると考えがちであるが、よくよく見てみると本当に特別なことをしている会社は少ない。優位性を保ち続ける会社がやっていることは誰にでもできることである。しかし、他社と違うのは、誰にでも出来ることを誰にも出来ないレベルで徹底し継続してやっているということである。そこには、秘策や奇策もなく当たり前のことを当たり前にやり続けることその継続する力、徹底する執拗さ等がやがて革新的な力に結実していく。フォーカスしてそこに経営資源を集中することが強みにつながる等といったセオリーは、経営に携わる多くの人は、論理や頭では十分理解出来ている。然しながら、現実となるとこれが非常に難しい。フォーカスするということは、やらないこと、捨てることを決めなければならない。この「やらないこと」「捨てる」ということが、実は容易なことでない。何故ならば、フォーカスする、即ち絞り込みには「狭さ」の限界がつきまとうという懸念がある。「二兎を追う者は一兎をも得ず」とは言っても、狙う「一兎」が小さすぎはしないかということであろう。捨てるもう一兎にビジネスチャンスがあるのに、そこに利益を獲得できるチャンスがあるのに敢えて捨てるということ難しさ、これが現実であろう。真に優位性を構築している企業が他社と違うところがあるとすれば、誰にでもできること、誰にでも考えられることを、誰にも出来ないレベルで徹底してやっているということではないだろうか。現実には、「一兎を徹底して追うものは結果的には二兎を得る」というのが、多くの成功した戦略のパターンになっている。集中あるいは絞り込みが、「狭さ」というデメリットだけを持つのではない。集中や絞り込みを行なうからこそ、成功が生まれ波及効果が生まれ、究極的には大きなメリットが出るのである。第一の考え方の例は、他分野で蓄積した技術の転用、ブランドや流通網の利用、あるいは自社の余剰な資源の利用(たとえば遊休設備)などである。第二の考え方は、資源の集中のパターンで競争相手との差をつくることである。例えば、価格差別化を武器にしようと思ったら、そのための資源投入を競争相手よりうんと集中的にやることである。製品開発も大事、流通網も大事なのは確かだが、あえて他を犠牲にしてもコスト競争力をつけるために資源を集中するのである。何でも大事な経営は、結果的に何も大事にしていないのである。